バリュー株投資とは何か(1)
これからしばらく、基本に立ち返り「バリュー株投資とは何か」について順を追って解説したいと思います。これを読んで理解を深め、資産形成の一助としていただければ幸いです。

これからしばらく、基本に立ち返り「バリュー株投資とは何か」について順を追って解説したいと思います。これを読んで理解を深め、資産形成の一助としていただければ幸いです。

任天堂決算に関する代表・栫井のコメントが毎日新聞に掲載されました。 売上高2.5倍 「スイッチ」好調 4~6月期(毎日新聞) 一方、つばめ投資顧問の栫井駿介代表は「家でも外でも遊べる新型機なら発売当初はこのくらい売れて当…

バリュー株投資では、企業が持つ「本質的な価値」を導き出すことが最初の一歩となります。私も推奨銘柄の「目標株価」として適正な価値を示していますが、実際の価値は特定の株価で示せるほど単純なものではありません。

マネーボイスに以下の記事を寄稿しました。ぜひお読みください。 誰が日本のパチンコを殺すのか?出玉規制とカジノ解禁のカラクリを読む

有料会員向けに推奨していたダイト(4577)を昨日売却推奨し、推奨時から35%の利益を確保しました。

任天堂(7974)の株価が大きく上昇しています。2017年4月以降の上昇率は40%にのぼり、「Wii」が大ヒットを記録した2008年以来の高水準です。時価総額は5兆円を超えました。

私が数ある選択肢の中からバリュー株投資を選好するのは、自分が知りうる限り最も確実性が高く、良好な成果を残せると確信しているからです。その理由は、単にバフェットが行なっているというだけではなく、日本株における長期パフォーマ…

バフェットが、経営難に陥ったカナダの住宅金融機関ホーム・キャピタルに出資し、すでに90%のリターンをあげたとのことです。最近はAmazonやGoogleなどの成長企業への羨望を口にしますが、彼の本質は師匠のベンジャミン・…

今週、当社ホームページでタカタ(7312)について取り上げました。 https://tsubame104.com/2017/06/21/%E8%B2%B7%E3%81%86%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%81…

タカタ(7312)が急落しています。6月16日に民事再生法申請に向けて最終調整が行われていることが報じられてから3日連続でストップ安となり、現時点(6月21日)でも止まる様子はありません。
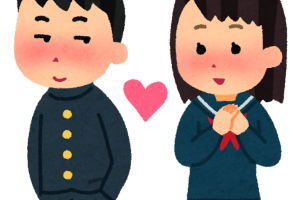
リンクの記事をマネーボイスに寄稿しました。ぜひご覧ください。 ファミマとドンキの「熱愛発覚」を分析してわかった意外な好相性
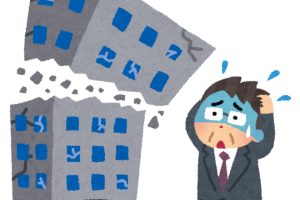
世界の景気は、この10年間で最高と言える水準に達しています。失業率は低下し、日本やアメリカ、ドイツなどの先進国では完全雇用に近い状況です。 この好調な景気には、複数の要因があると考えています。

私が行うバリュー株投資は「資産運用」というよりも「プロジェクト」だと考えています。資産運用は相場の流れに身を任せるものですが、プロジェクトは自らの意志で前に進むものです。

バリュー株投資は、基本的には「長期投資」です。しかし、単に同じ銘柄を長く保有していればもうかるというものでもありません。場合によっては、買ってから比較的短期で売却を判断することもあります。

日経平均株価は1年半ぶりに20,000円を突破し、米株式市場も史上最高値の更新を続けました。市場は楽観に包まれています。

新たな銘柄を選ぶとき、慎重を期せば期すほど、どこまで調べたら良いかわからなくなってしまいます。そして、いくら調べたところで将来のことは誰も正確に言い当てることはできません。 そうは言っても、株式投資に取り組む以上どこかで…

Amazonの株価が上昇を続けています。バフェットですら、Amazonへ投資しなかったことを「失敗だった」と言うほどです。この記事では、Amazonがなぜ伸びたのか、そしてまだ伸びるのかどうかを考えます。

投資の世界ではよく「ファンダメンタルズ」という言葉が使われます。インターネットで調べると、以下のような説明にたどり着きます。 ファンダメンタルズとは、国や企業などの経済状態などを表す指標のことで、「経済の基礎的条件」と訳…

トランプ大統領の弾劾のリスクが高まったことから、市場は弱気に転じています。しかし、最近の好調な相場は期待先行の危ういものであり、トランプ政権のおぼつかなさを見れば十分に予見できたことです。

関西電力(9503)の株価が上昇しています。上昇率は1年で約5割にのぼります。